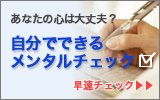アロマで花粉対策。アロマテラピーを花粉対策に活用 - [アロマオイル(精油)の通販専門店アロマ・タイム]
【営業日のご案内】
| 2026年02月の定休日 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年03月の定休日 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
グレー■:終日休み
※日中不在のため、お問合せはメールにてお願いいたします。

アロマで花粉対策

春が近づいて来るのはうれしいですね。でも、、、花粉症の方々にとってはいやーな時期でもあります。花粉症の人口は年々増えているようで、子供の花粉症も珍しくありません。
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみそんな辛い不快感をアロマオイルは和らげてくれます。アロマオイルを活用して花粉に勝つ体を作りましょう!
アロマ入りのマスクスプレーでスッキリ!
外出する際マスクをされる方も多いと思います。
マスクにシュッとひとふきして装着すればムズムズ鼻もスッキリ爽やか。
【マスクスプレーの使い方】
マスクの内側にスプレーし、マスクを軽く振ってなじませてから装着します。
※お肌が敏感な方はマスクの外側にスプレーしてください。
【番外編】
通常のアロマオイルを、マスクの外側の端に少量つけて装着する方法も手軽です。

アロマバスで鼻づまり解消
お風呂にゆったり浸かりながら花粉に強い体を作りましょう。
【おすすめのアロマオイル(精油)】
■ユーカリラジアタ:1.8シネオールという成分が鼻の炎症を緩和し通りをよくすると言われています。
■カモミールローマン:成分に含まれるアンジェリカ酸イソアミルやアンジェリカ酸イソブチルに抗アレルギー作用があると言われています。
【アロマバスの方法】
お湯を張った浴槽に上記のアロマオイルどちらかを2滴とラベンダー1滴を入れ、よくかき混ぜてから入ります。

シアバターやキャリアオイルで肌の乾燥対策
肌が乾燥するとバリア機能が失われ、そこに花粉がつくとかゆくなることがあるそうです。
シアバターやキャリアオイルで乾燥からお肌を守りましょう。
【保湿の方法】
シアバターやキャリアオイルを手に取り、少し温めてから腕や足など全身に伸ばしていきます。

かみすぎて荒れてしまった鼻下に
鼻をかみすぎて痛いという方にはスキンバームがおすすめ。マリーゴールド、ミツロウ配合でお肌を優しくケアします。
ペパーミント、ユーカリラジアタなどの精油配合ですっきりとした清涼感ある香りです。
精油は医薬品ではなく、医療行為に代わるものではありません。現在の身体状況や治療・投薬等については医師の指示に従ってください。当サイトはアロマテラピーに関する行為によって生じたいっさいの損傷、負傷、その他についての責任は負いかねます。十分にお気をつけになってお楽しみくださいませ。
![]()
精油の使用回数について
・10mlの精油 200滴
・5mlの精油 100滴
一般的なドロッパーは1滴=0.05mlなので、意外とたくさん使えます♪
![]()
数年ぶりのコロナ
寒波が長く続いた一月下旬。
久しぶりに発熱したため病院に行って検査をしたところ、コロナでした。。。
二、三日前から頭痛とあまり感じことのない肩こりを覚え、
流行っているインフルエンザかなと思いましたが、まさかコロナとは。トホホ。
大寒波の日に京セラドームで行われたレディーガガのライブに行ったので、原因はこれでしょう。
(ちなみにガガは圧巻のパフォーマンスでした!)
2回目のコロナはあまり高熱もでず、何だか風邪っぽい。
前回のように食欲不振・味覚障害もどこえやら、ご飯も普通に食べられました。
ただ、鼻詰まりがヒドイ。。。
動いているとマシなのですが、寝ていると両方鼻が詰まっていき、く、く、苦しい。。。
そこでティートリーをティッシュにつけて吸入してみたところ、鼻通りが良くなりました。
喉の痛みにも効きますし、さすが殺菌力の強い精油。
ティートリーは以前旅行先でのどが痛くなった時にも吸入し、ことなきを得ました。
ラベンダー同様万能精油であり、1本あると本当に便利ですよ。

2月は寒さに加え、花粉の飛散もありますね。
花粉症の方はユーカリがおすすめです。

まだまだ寒さ厳しいですので、みなさまどうぞご自愛ください。
→過去のちょっとコラム

















![ネロリウォーター[全身用化粧水]](../photo/CH325m.jpg)