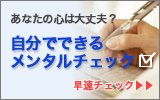アロマの歴史に関する情報 - [アロマオイル(精油)の通販専門店アロマ・タイム]
【営業日のご案内】
| 2026年02月の定休日 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年03月の定休日 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
グレー■:終日休み
※日中不在のため、お問合せはメールにてお願いいたします。

アロマの歴史
各国、各時代のアロマオイル(精油)の歴史を紹介いたします
古代より、香りは主に神への捧げもの、死者への弔い、病人への薬、異性への媚薬等に使われてきました。
エジプト
エジプトでは、太陽の神Ra(ラー)に、香煙に乗って魂が天国へ導かれるようにと祈りの儀式に用いられていました。時刻によって焚かれるものは異なっており、朝は日の出と共にフランキンセンス(乳香)、正午にはミルラ(没薬)、日の沈むときにはキフィ(キピ)と呼ばれる16種類の香りをブレンドしたものが焚かれたといわれています。ユリ油が入ってる「ザグディ」は珍重され、「メンデシウム」と呼ばれる香油にはバラノス油(ホースラディッシュツリーの実の油)とミルラやフランキンセンスが入っていました。
B.C.3000〜B.C.2000頃の石膏やオニキスやガラスや象牙や木でできた軟膏や香水入れが見つかっており、その中にはミルラ、フランキンセンス、シダーウッド、オレガノ、アーモンド、カンショウ(甘松)、ヘンナ、ジョニパー、コリアンダー、カラマスなどのエジプトで採れる植物の香りの軟膏や香水が入っていたといわれています。
そして、エジプトで忘れてはいけないのがミイラです。死者の魂が蘇った時に肉体が必要であろうという思いから死体を保存したものです。その制作過程でもミルラやシダーウッド等のたくさんの香料が使われていました。そして、ミイラの語源は現在アロマテラピーでも用いることのできる「ミルラ」だと言われています。
また、絶世の美女と言われているクレオパトラはその美貌や教養だけでなく、香りの力を実にうまく利用し異性を魅了していたと言うことです。彼女はバラの花を愛したことで有名で、室内に厚さ46cmもバラの花を敷き詰め、またセクシーで香りが後々まで残る動物性香料のムスク、シベットを愛用していた様です。

ミルラ

フランキンセンス
イスラエル
イスラエルでも、神への捧げ物の作物や羊などにフランキンセンスが添えられたりと、神と人をつなげる役割で使われていました。
B.C.960〜B.C925頃ソロモン王にアラビア南部のイエメンにあったシバの女王の国から「香料の道」を北上し、黄金とフランキンセンスとミルラが献じられたとあります。また、新約聖書のマタイの福音書第2章、キリスト誕生の場面にもアロマテラピーにでてくる精油の名前がでてきます。
「東方の三使者が聖母マリアのそばにいる幼子にひれ伏し、黄金(偉大な商人のシンボル)、フランキンセンス(偉大な予言者のシンボル)、ミルラ(偉大な医者のシンボル)の貢ぎ物を捧げた」とあり、その時キリストはフランキンセンスを選んだといわれています。
古代ギリシャ
古代ギリシャでは、B.C.4世紀頃から、香りについての科学的な研究が行われ、テオフラストス(B.C.370〜B.C.285年ごろ)が「植物史」を著しています。その中には、フランキンセンスやミルラの生育・栽培についても記述しています。

シナモン
古代ローマ
古代ローマでは、バラが生活に密着しており、色々な儀式や晩餐会でまかれ、宮廷の泉にはバラ水が湧き、公衆浴場までもバラでいっぱいでした。また、衣類までもがバラ水で洗っていたということです。生活が豊かになるに伴って、香料も流行となりました。
イスラム
ローマ帝国が滅び、ローマ時代の文化を引き継いだのはイスラム文化でした。
女性は王様に逢うためには12ヶ月の「お清めが」必要とされ、最初の6ヶ月はミルラの香油を用い、後半の6ヶ月は他の何種類かの香油が用いられていました。また、砂漠地帯に暮らす人々はなかなか入浴ができなかったため、デオドランド剤としてミルラなどの香油を浸した布を胸元にしのばせておいたそうです。
中世・近代ヨーロッパ
6世紀〜17世紀にヨーロッパで香りの文化が発展していきました。
アルコールの発見、蛇管と蒸留器の発明により、花本来の香りを抽出し保存する事が可能になったり、バラから精油とバラ水が取れることが発見されました。そして、ベニスの商人により香料の貿易も盛んに行われ、香料貿易も世界規模になりました。
また、これまで口で伝えられてきたアロマテラピーも16世紀に入ると、「新完全蒸留読本」や「植物読本」などの様々な書物が書かれ、アロマテラピーはこの頃、体系づけられました。

現代
香りは主に香水の文化で用いられており、18世紀〜19世紀のヨーロッパの貴族の間ではなくてはならない物となり、調香師を雇い、特注の香水を造らせていたことも珍しくはありませんでした。
ポンパドール婦人とマリ−アントワネットはジャスミン、ローズ、バイオレット等のフローラル系を好み、ルイ14世はローズウォーターとマージョラムで部屋を香らせ、衣類はクローブ、ナツメグ、アロエ、ジャスミン、オレンジウォーターで洗わせました。
![]()
精油の使用回数について
・10mlの精油 200滴
・5mlの精油 100滴
一般的なドロッパーは1滴=0.05mlなので、意外とたくさん使えます♪
![]()
数年ぶりのコロナ
寒波が長く続いた一月下旬。
久しぶりに発熱したため病院に行って検査をしたところ、コロナでした。。。
二、三日前から頭痛とあまり感じことのない肩こりを覚え、
流行っているインフルエンザかなと思いましたが、まさかコロナとは。トホホ。
大寒波の日に京セラドームで行われたレディーガガのライブに行ったので、原因はこれでしょう。
(ちなみにガガは圧巻のパフォーマンスでした!)
2回目のコロナはあまり高熱もでず、何だか風邪っぽい。
前回のように食欲不振・味覚障害もどこえやら、ご飯も普通に食べられました。
ただ、鼻詰まりがヒドイ。。。
動いているとマシなのですが、寝ていると両方鼻が詰まっていき、く、く、苦しい。。。
そこでティートリーをティッシュにつけて吸入してみたところ、鼻通りが良くなりました。
喉の痛みにも効きますし、さすが殺菌力の強い精油。
ティートリーは以前旅行先でのどが痛くなった時にも吸入し、ことなきを得ました。
ラベンダー同様万能精油であり、1本あると本当に便利ですよ。

2月は寒さに加え、花粉の飛散もありますね。
花粉症の方はユーカリがおすすめです。

まだまだ寒さ厳しいですので、みなさまどうぞご自愛ください。
→過去のちょっとコラム






![ネロリウォーター[全身用化粧水]](../photo/CH325m.jpg)